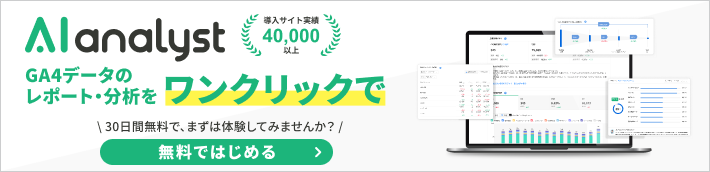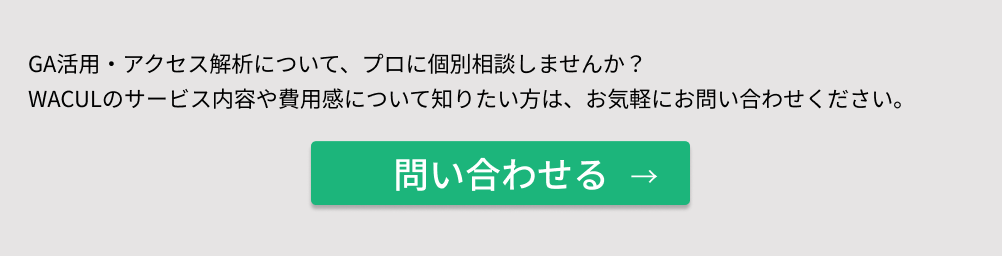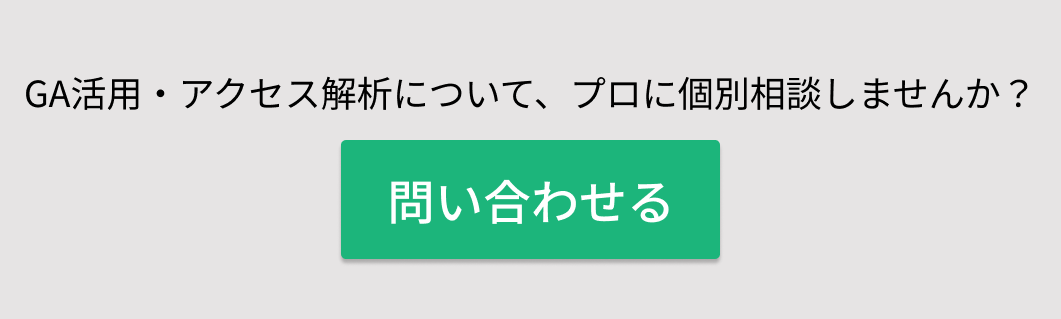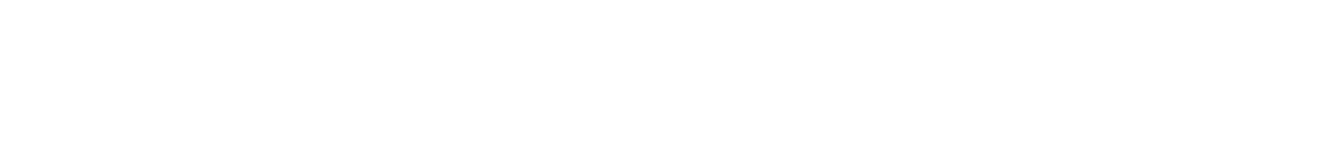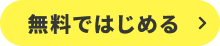SHARE 0
SHARE 0
ホームページのアクセス解析でどこまで分かる?得られる情報や活用方法などを解説
アクセス解析 |
こんにちは。「AIアナリスト」ライターチームです。
ホームページを運用しているものの、アクセス解析がどのようなものなのか、どのような情報を取得できるのか詳しく知らない人もいるのではないでしょうか。この記事では、自社サイトのアクセス解析によってどのような情報を得られるのか解説します。ホームページの改善やマーケティングに役立つ情報なので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
- アクセス解析とは
- アクセス解析を行う目的
- ホームページのアクセス解析に使用するツール
- アクセス解析を行う際に利用したい「タグマネージャ」とは?
- Googleアナリティクスのアクセス解析で分かること
- アクセス解析によって得られた情報の活用例
- まとめ
アクセス解析とは
アクセス解析とは、自社サイトを訪れたユーザーの行動や属性などを分析することです。ホームページを訪問するユーザーの属性や、ホームページ内でのユーザーの行動、参照元などを解析し、コンテンツ作成ホームページの改善、マーケティング活動などに活用します。
アクセス解析を行う目的
アクセス解析を行う主な目的は、解析によって得た情報をホームページの改善やマーケティング活動などに活用することです。アクセス解析では、ユーザーの行動や属性の分析こそ行いますが、これらの分析は個人情報の取得を目的としたものではありません。
ホームページのアクセス解析に使用するツール
ここでは、自社ホームページのアクセス解析を行う際に使用できる主なツールについて解説します。
Googleアナリティクス
ホームページのアクセス解析には、Googleアナリティクスを使用するのが一般的です。GoogleアナリティクスはGoogleか提供するアクセス解析ツールであり、無料版と有料版があります。ツールを利用することで、ユーザーの利用状況がリアルタイムにわかるほか、基本属性やどこから訪れているのかといった情報の把握も可能です。
Googleが提供する他のツールとの連携もできるなど、使い勝手の良さは大きな特徴だといえます。Googleアナリティクス以外にも、各企業が提供するアクセス解析ツールがあります。
Googleアナリティクスの導入方法
Googleアナリティクスを導入する場合、アナリティクスアカウントを作成する必要があります。具体的な流れは以下の通りです。
アクセス解析を行う際に利用したい「タグマネージャ」とは?
アクセス解析を行う際には、合わせてGoogleタグマネージャと呼ばれるツールを使うことで、タグ管理が行えるようになるためおすすめです。タグとは、制御情報のことであり、Googleタグマネージャを使用すれば、タグを設置・削除を一元管理できます。
タグマネージャは、ホームページに広告タグを設置する場合やマーケティングオートメーションツールを利用する際などにスムーズに対応できるというメリットがあります。
なおタグやGoogleタグマネージャについては以下の記事で詳しく紹介しているのでこちらもご覧ください。
タグとは? HTMLタグ・コンバージョンタグ・ツール用タグの違いを解説!|アクセス解析ツール「AIアナリスト」ブログ
Googleタグマネージャ完全ガイド【導入メリットから使い方まで丁寧に】|アクセス解析ツール「AIアナリスト」ブログ
Googleタグマネージャの導入方法
Googleタグマネージャを導入する際の具体的な手順は以下の通りです。
Googleアナリティクスのアクセス解析で分かること
ここでは、Googleアナリティクスを使ったアクセス解析でどのようなことがわかるのか具体的に解説します。
ユーザーの流入経路
アナリティクスを利用すれば、ユーザーがどこから訪れているのか流入経路を把握できます。具体的には検索、SNS、広告などが流入経路となります。流入経路はリアルタイムレポートから確認できます。リアルタイムレポートでは、流入経路以外にも、リアルタイムでユーザーの情報が把握可能です。
アクセス数(PV数)
アクセス数とは、ホームページがブラウザ上に表示された回数のことです。例えば、トップページと会社概要、企業理念の3つのページを閲覧するとアクセス数は3となります。アクセス数はページビュー数から確認可能です。ちなみに、アクセス数はセッション数と照らし合わせるとユーザーがページを連続して閲覧しているかがわかります。
検索キーワード
アナリティクスでは、ユーザーがどのような検索エンジンでどのようなキーワードを入力してホームページを訪れているのかという、検索キーワードを把握できます。検索キーワードは、集客レポートから確認可能です。集客レポートでは検索キーワード以外にも、ブックマーク経由のアクセスやSNS経由のアクセスがどのくらいなのかもわかります。
ユーザーの行動
ユーザーの行動とは、ホームページを訪れたユーザーのサイト内における行動のことです。例えば、どのページを最初に閲覧しているのか、どのページを最後に閲覧したのか、どのくらいの時間滞在していたのかといったことがわかります。これらの情報は行動レポートから把握でき、行動レポートではそのほかにもユーザー数や離脱率なども把握可能です。
ユーザーの属性
ユーザーの属性とは、ユーザーの年齢や性別、アクセスした地域などの情報のことです。こちらは、オーディエンスレポートから把握できます。オーディエンスレポートでは、そのほかにも、セッション数やページビュー数、さらには直帰率やどのデバイスを使用していたかといった情報も把握可能です。
目標に対する結果
目標に対する結果は、ホームページを訪れたユーザーに起こしてもらいたい行動がどのくらい達成されているかを示しています。この情報はコンバージョンレポートから把握可能です。なお、コンバージョンレポートではそのほかにも、どのページを閲覧した人が行動を起こしやすいのか、どのような毛色が行動につながるのかといった情報もわかります。
アクセス解析によって得られた情報の活用例
ここでは、実際にアクセス解析を行って得た情報をどのように活用するのか、具体的な例をあげながら解説します。
直帰率が高い場合
直帰率とは、最初に訪れたページのみを閲覧しホームページから離脱した割合を示します。最初に見たページでユーザーのニーズが満たされているケースもあるため、直帰率が高いからといって必ずしも悪いわけではありません。
ただし、トップページの直帰率が高い場合は、何かしらの改善が必要だと考えられます。例えば、ユーザーのニーズを改めて考えてみる、ホームページのレイアウトやメニューがユーザーにマッチしているか検討するといった改善策が考えられます。
直帰率に関しては以下の記事で詳しく解説しているため、こちらも参考にしてみてください。
直帰率とは|離脱率との違いや目安を徹底解説!|アクセス解析ツール「AIアナリスト」ブログ
離脱率が高い場合
離脱率とは、ホームページを訪れたユーザーがどのページで離脱しているのかを表す割合のことです。離脱率を確認する際は、どのページで割合が高いのかが重要です。
例えば、コンバージョンにつながるページでの離脱率が高い場合、ユーザーが商品やサービス、ホームページに魅力・興味を感じていない可能性があります。また、情報入力のフォームが使いにくいケースも考えられるでしょう。このような場合、トップページのデザインや情報入力フォームの見直し、項目数の再考などが必要だといえます。
目標(コンバージョン)の計測ができていない場合
Googleアナリティクスでは、コンバージョンの計測ができますが、中にはコンバージョンがアナリティクスに反映されないケースもあります。このような事態は、電話での問い合わせや、問い合わせが完了した際の画面が用意されていない、といった場合に起こります。そのため、ホームページ内で完結する問い合わせ形態にするほか、問い合わせ完了時の画面を用意するなどの対策が必要です。
まとめ
アクセス解析を行うことで、ユーザーの属性や行動などホームページ内における詳細な情報を把握できます。集めた情報はホームページの改善やマーケティング活動に活用できるため、ホームページを運用している企業はぜひアクセス解析に取り組んでみてください。なお、アクセス解析を行う際はプロの力を借りるのも1つの方法です。
「AIアナリスト」は、AIがアクセス解析を⾃動で⾏い、重要な改善ポイントを教えてくれるツールです。これまでに30,000サイトを改善したノウハウで、ホームページの膨大なデータを分析し、成果を伸ばすための改善ポイントをデータ根拠とともにお届けします。Googleアナリティクスに連携するだけで利用可能で、設定は2分で終わります。
まずは無料版からお試しください。
この記事を書いた人

株式会社WACUL
株式会社WACUL(ワカル)は、「Webサイト分析をシンプルに」というビジョンのもと、簡単にWebサイト改善の方針を手にすることができる世の中を実現します。

この記事を書いた人
株式会社WACUL